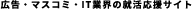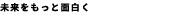編集者は“視点”を届ける仕事。文藝春秋『文學界』編集長に聞く役割とは
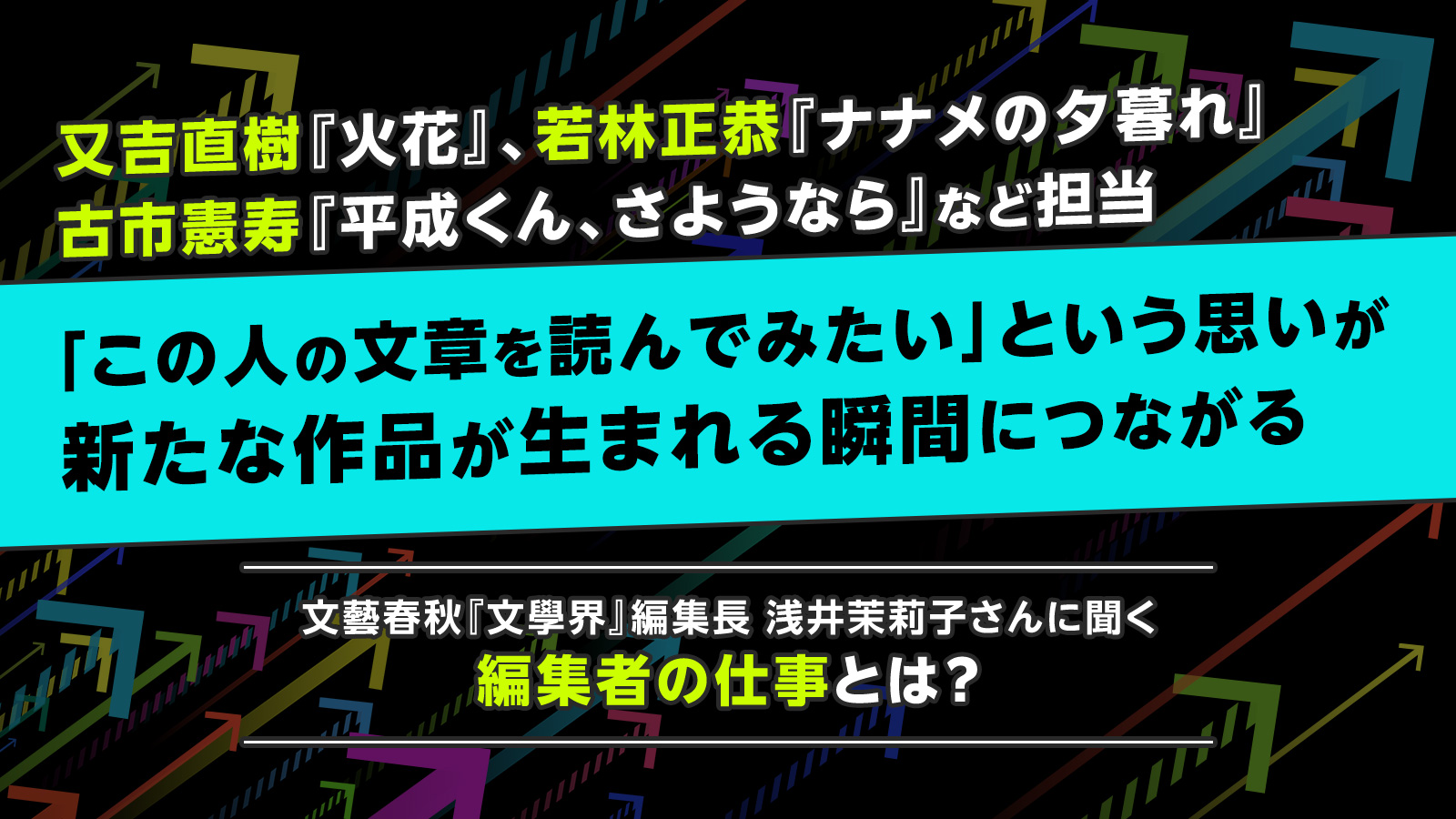
クリエイターが何かを生み出す裏側には、世の中に発信するプロデューサーが必ずいます。小さなタネを「育てる」「広げる」「すすめる」「まとめる」「実行する」「解決する」役割を担っています。2025年2月、そんなプロデューサーにフォーカスした「プロ活フェス」を開催し、文藝春秋『文學界』編集長の浅井茉莉子さんに公開インタビューを行いました。編集者は執筆者に伴走し、その作品の可能性を広げて一つの作品としてまとめ、世の中に送り出しています。その仕事はまさにプロデューサー。今回は、記者・小説の編集者、文芸誌の編集者として幅広く経験した浅井さんの視点から、編集者の仕事やスタンス、求められる力のヒントをお聞きしています。
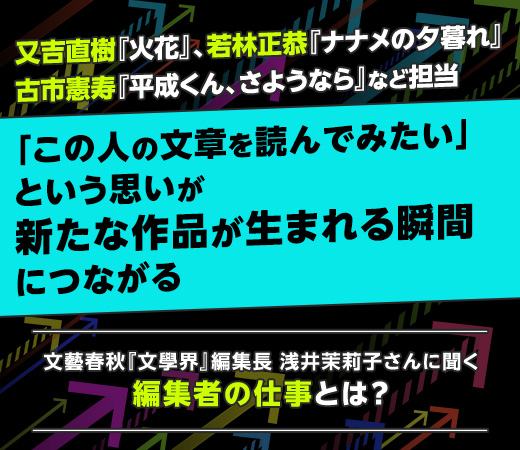
- 浅井茉莉子さん文藝春秋『文學界』編集長
- 1984年生まれ。早稲田大学第一文学部を卒業後、2007年に文藝春秋に入社。『週刊文春』、『別冊文藝春秋』、第二文藝部を経て、2023年7月から『文學界』編集長。
担当作品:村田沙耶香『コンビニ人間』、又吉直樹『火花』、若林正恭『ナナメの夕暮れ』、松尾諭『拾われた男』など
- 【 目次 】
- 週刊誌記者から文芸誌編集者へ
- あの人のこんなテーマの文章を読んでみたい、から始まる
- 行動し続ければ、新たな作品が生まれる瞬間に立ち会える
週刊誌記者から文芸誌編集者へ
——浅井さんのこれまでのキャリアについて教えてください。
2007年に文藝春秋に新卒入社し、最初の2年間は『週刊文春』で記者を経験。事件現場での取材や張り込みなど、まさに“足で稼ぐ”仕事でした。その後、エンタメ小説の編集、文芸誌『文學界』の編集部の行き来などを経て、現在は『文學界』の編集長を務めています。
——入社してすぐ週刊誌記者になりましたが、その経験は編集者の仕事にも活きていますか?
活きていると思います。記者の仕事は、自分とはまったく違う人生を歩んできた人の話を聞くことです。記者として相手のことをどう調べるか、どう深堀りして聞き出すかを学びました。その経験から身についた、調べる力・想像する力・人と話す力は、小説家との対話や原稿を深く読み込む場面で大いに役立っています。編集者になってからも、「人の話を聞く力」は変わらず大切だと感じますね。
あの人のこんなテーマの文章を読んでみたい、から始まる
——文芸誌の編集者は、どのようなことをしているのですか?
文芸誌『文學界』では、毎月いろいろな方の小説を掲載しながら、特集ページの企画もつくります。今まで考えた特集では、「笑ってはいけない?」「声と文学」「無駄を生きる」といった、ジャンルを超えた人たちが登場するような、文芸誌としては変化球のテーマも手がけました。
特集では、自分自身が興味関心をもっていること、もしくは会いたい人や気になる人を中心にアイデア出ししていくことが多いです。個人の興味から出てきたものを、面白がってくれる人がたくさんいるといいなと思っています。例えば「笑い」をテーマとしたとき、文芸誌ではどのような角度から取り上げられるんだろうという視点から考え、「笑ってはいけない」というタイトルが思い浮かびました。ここから「笑い」に対して、文芸誌ならどういうアプローチができるか、どんな人に出てもらったら面白いかを考え、依頼する人をリストアップしていきます。
正直、編集者=プロデューサーと思ったことはないんです。ただ「ある物事に対して、あらゆる視点を持って切り口を考える」という点が、編集とプロデュースに共通してあるのではないでしょうか。上述の雑誌の特集決めや後ほどお伝えする新たな書き手への執筆依頼もそうですが、「ある物事に対して、誰に、どんな切り口で、何を届けるか」を考えて企画をつくるのは、プロデューサーと同じことなのかもしれないですね。
——企画の源泉を教えてください。
文芸誌の特集に限らずですが、やはり企画の着想としては、自分が“気になっていること”がきっかけになりやすいです。「この人、面白そうだな」「このテーマ、もっと知りたいな」という純粋な興味が出発点になることが多いですね。情報収集として行っているのは、普段からスマホのメモに気になった人や言葉を残しておき、後から調べること。ただ自分の視野から得られる情報だけでは限界もあります。いろいろな人に会って、その人たちが気になっていること、面白いと思っていることを聞くことも心がけています。
また、いままで小説を書いたことがない、新しい書き手を常に探しています。発掘というと大げさですが、基本的には企画を考えるときと同じで、文章を読んで、もっと読みたい、一緒に仕事をしてみたいと思った方に、依頼をしています。私が「良いな」と思うポイントは、文章にその人の考えや見ているものが落とし込まれている、つまりその人なりの視点があるかどうか、だと思います。
行動し続ければ、新たな作品が生まれる瞬間に立ち会える
——『火花』(又吉直樹さん)など、専業作家以外が手がける話題作にも関わってきたそうですね。
又吉さんの場合、別冊文藝春秋を読んでいるとブログに書かれていたのを見て、「この人、相当な小説好きだ」と気になっていたんです。ちょうど文学フリマというイベントで偶然お会いしてご挨拶した後、お手紙で小説執筆を依頼しました。すぐに「はい、わかりました。書きましょう」と話が進んだわけではありません。小説への敬意がある方だからこそのためらいがあったと思います。なので、焦らずに「いつでも待ってますよ」と伝えていました。そうして何度もお会いしているうちに、作品を書いてもらえることになったんです。
担当編集がついている既存の作家の方たちだけではなく、又吉さんのように本業が作家ではない方にお声がけをすることも多々あります。例えば若林正恭さんの『ナナメの夕暮れ』や松尾諭さんの『拾われた男』、社会学者の古市憲寿さんの『平成くん、さようなら』などの作品を手がけてきました。
偶然の出会いから生まれる作品もあります。もちろん、作品として完成しないことも少なからずあります。小説を書くのはやっぱり難しいことだと感じます。しかし、まずは書いていただく気持ちを共有しないと、新たな作品が生まれる瞬間に立ち会うことはできません。大事なのは、その人が「今なら書ける」と思えたタイミングに、そばにいることだと思います。それを信じて待つだけです。
また、編集者として伴走する際には、書いていただいたものに対して敬意をもって、伝えるべきことは伝える、というスタンスを大切にしています。小説には正解がありません。編集者が言うことが正しいわけではないですし、あくまで一個人の捉え方で、指摘したからその通りにしてほしいというわけでもない。いろいろな可能性を話し合う相手として、編集者はいるのだと思います。数ある可能性の中から最終的に選び取るのは、作家の方自身ですから。
——編集者に向いているのは、どんな人だと思いますか?
一言で言えば、行動する人。「この人に会ってみたい」「こういうテーマを形にしたい」と思ったときに、恐れず一歩を踏み出せる人ですね。
でも編集者は十人十色。人それぞれのやり方があるので、全体に共通する特徴を挙げるのはなかなか難しいですね。あえて一つ挙げるのであれば、人に会うのが嫌いな人はあまりいない、ということかもしれません。文藝春秋の場合ですが、1人で30〜40人の作家を担当しています。いろいろな人と向き合っていく覚悟と行動力が求められます。学校の先生のようなイメージが近いかもしれません。いろいろな人がいて、各々との関係性も違いつつ、全体を見通して進めていくような印象があります。
—— 最後に、学生へのメッセージをお願いします。
なんか好きだな、気になるなと思ったことがあったら、まずは動いてみてください。学生時代は自由な時間があるからこそ、自分の“好き”を深掘りできるチャンスです。何かをつくる仕事って、本当に楽しいと思います。
また、文芸誌や出版業界の未来は、正直明るい話ばかりではないです。でも、文芸誌ってとても“自由”な場だと思います。昔から専業の作家だけではなく、さまざまな職業の方が小説を書いてきました。そうした開かれた土壌が、今も脈々とつづいているのが文芸誌です。そこに少しでも興味をもってくれる人が増えたらうれしいです。