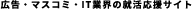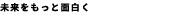「やりたいこと」を武器に変える就活を。元TBSディレクターが語る、“企画で突破するキャリアの築き方”

2025年2月、クリエイターを目指す学生のための就活イベント「クリ活フェス」(マスナビ主催)にて元TBSテレビで現在はフリーの映像ディレクターとして活躍する大前プジョルジョ健太さんに公開インタビューを行いました。「番組をつくるって、どんな仕事?」「就活の企画課題って、何をどう書けばいいの?」そんな疑問を持つ学生に向けて、報道・情報・バラエティーまで幅広い現場を経験した視点から、テレビの仕事のリアル、そして就活でも活かせる「伝え方」のヒントをお聞きしています。本レポートでは当日の公開インタビューの様子をお届けいたします。
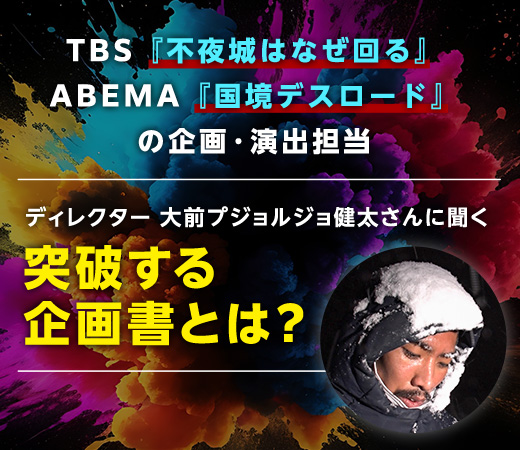
- ディレクター 大前プジョルジョ健太さん
- 1995年4月11日大阪府大阪市生まれ。法政大学社会学部社会学科卒業後、TBSに入社。『あさチャン!』など朝の情報番組を担当後、報道局経済部で記者を経験。2021年から『ラヴィット!』『サンデー・ジャポン』などの情報バラエティー番組を担当。自身が企画した『不夜城はなぜ回る』は、2023年1月に優れたテレビ番組を表彰する「ギャラクシー賞」月間賞や「2023年日本民間放送連盟賞」の「テレビエンターテインメント」部門で優秀賞を受賞し話題を呼んだ。2024年1月にTBSを退社。同年12月からはABEMA新番組『国境デスロード』の企画・総合演出を務める。
- 【 目次 】
- 報道と情報の違い
- 絵が見える企画かどうか
- コンテンツインなテレビ局とマーケットインな配信サービス
報道と情報の違い
──今までのご経歴を教えてください。
学生時代は報道とバラエティーを両方志望しており、TBSテレビに入社しました。入社後は朝の情報番組、報道局経済部の記者を経験した後、昼の情報バラエティー番組を担当。現在はフリーのディレクターとして、ABEMA番組『国境デスロード』の企画・総合演出などを務めています。
──テレビ局の仕事は、ジャンルによってどのように違いますか?
僕が経験した報道と情報の違いについて触れると、報道は一次情報を取りに行くのが仕事です。新聞記者に近い役割で、事件や政策を現場で取材して情報を得ます。どこよりも早く正確な情報集めが大切になるため、カメラは持たずひたすらニュースになる素材集めをするイメージです。そして集めた情報を視聴者にわかりやすく説明するためにカメラマンが映像を撮り、その素材をエディターが編集し、ニュースになります。
一方、情報番組は、報道で得た素材をもとに、街頭インタビューなどの追加取材を行って、視聴者にわかりやすく伝えます。報道の素材だけでは番組が成り立たないので、情報番組のディレクターは、追加取材を行うためカメラを使用し、編集まで行うのが大きな違いです。
また、報道はどこよりも早く情報を得るという方針が根強いですが、僕はそのメリットをあまり感じていません。確かにその熱量は大切ですが、僕自身は情報の先に番組の絵、つまり「視聴率が取れるか」を意識した取材を行っていたんです。情報番組に流す前提の報道記者という感じでした。報道デスクと日々接していると、今は視聴率への意識が強くなっている印象を受けます。「これを報道したい」という正義ももちろん必要ですが、同時に映像の強さが求められる時代になってきているのではないでしょうか。
絵が見える企画かどうか
──就活でよくある企画書をつくる課題に取り組むうえでのポイントはありますか?
TBSの選考で「書く」だけでなく実際に企画の映像を撮って見せたんです。それがすごく印象に残ったみたいで。企画は「絵が見えるかどうか」が大事。「これ、イメージできないね」と言われたらアウト。でも映像があれば、説明せずとも伝わります。就活の企画課題で、「企画案+ちょっとした映像」の形で見せるのは効果的です。現在の仕事でも、「絵が見える企画」にすることで説得力が増していると思います。
──TBSで最初に企画が通った番組は、どんな内容でしたか?
『不夜城はなぜ回る』という深夜に煌々と光っている建物(不夜城)に潜入する番組です。元々、人の家に入るのが好きで、深夜に明かりが灯っている家の中を覗いてみたいという思いがありました。それを「夜中に光っている建物では何をしているのか」という世間の関心と関連付ける企画にしました。入社5年目のときに企画が通り、企画・総合演出を担当しました。
──若手でも番組を持てるのですか?
番組を持てる可能性がいまめちゃくちゃ高まっています。YouTubeやNetflixなどさまざまな映像メディアがあるなかで、テレビ局に企画を出す人が減っていてチャンスです。番組をつくりたいという思いがあるなら、テレビ局は本当に狙い目です。
企画を通すコツは、とにかく数だと思います。まだまだ根性が試される業界なので、業務外で企画書をたくさん書いて、たくさん出す。僕は毎週のように構成作家と打ち合わせをして、企画案を考えて月に3本以上は必ず出していました。
──自分の企画アイデアを見せるのって、正直怖くないですか?
自分の企画アイデアを否定されると、自分が否定された気持ちになるから、もちろん怖いです。それでも見せる。人に話す。そうすると、誰か一人でも「面白い」と言ってくれたり、アドバイスをくれたりします。
僕は常に50人に聞くようにしています。ひたすら壁打ちです。アイデアのセンスがなくても、いろいろな人の話を聞けば、そこから良いところを吸収して面白い企画にブラッシュアップすることもできるから。50人のうち1人でも反応があれば、次につながります。
──今はABEMAで番組を担当されていますよね?
『国境デスロード』という、命がけで国境を越える人たちを追ったドキュメンタリー番組です。元々は「国境タクシー」という企画案でした。僕自身が国境周辺を走るタクシー運転手となり、国境を超える一般人の声を拾う構想でした。ただ就業ビザの関係で実現できず、現地のタクシー運転手を雇って撮ったパイロット編をABEMAのプロデューサーに見せたんです。最終的には、命がけで国境を超える「デスロード」の要素を加えて番組採用されました。ここで選ばれたのも、「すでに映像を撮っていて絵が見えていたこと」が効いたと思います。言葉より映像の説得力は強いです。
コンテンツインなテレビ局とマーケットインな配信サービス
──テレビ局と配信サービス、どちらも経験されていますが、それぞれどのような能力が求められていると考えていますか?
テレビ局は「こういう映像が見たいんだ」が許される環境があります。自身の関心ごとをド直球ではなくズラしながら企画・制作します。「自分のやりたいこと」をコンテンツに置き換えられる人材が重宝される。コンテンツインな考えです。
一方で、配信サービスはマーケットインの考え方が強いように感じます。視聴者が求めていることに寄り添っているか。またそれがどのように流通されるかを意識しています。SNSでバズる切り抜きの一枚の絵をつくれるか。見る前から面白そうと思ってもらえるか。もしかしたら広告クリエイターの考え方に近いかもしれません。
──これから映像業界を目指す学生に必要な力は何だと思いますか?
気合と足です(笑)。今、実際に足を動かせている人が少ないように感じます。だからこそ、自分で出向いたり、撮ったり、誰かに話したりできる、というだけで差がつくんです。特に映像は尺が長いので、間を埋めていくための物量勝負なところもあります。机の上で考えているだけでは形にならない。「まず動く」「形にして見せる」という姿勢が、就活でも仕事でもすごく大事になると思います。