RESEARCH業界・職種を学ぶ 就活・自分を知る
レポート
電通・博報堂・アクセンチュア・チョコレイトのクリエイターを講師にインターンを疑似体験「Creative Summer Camp 2024」開催〈イベントレポート〉
マスナビ×コピーライター養成講座
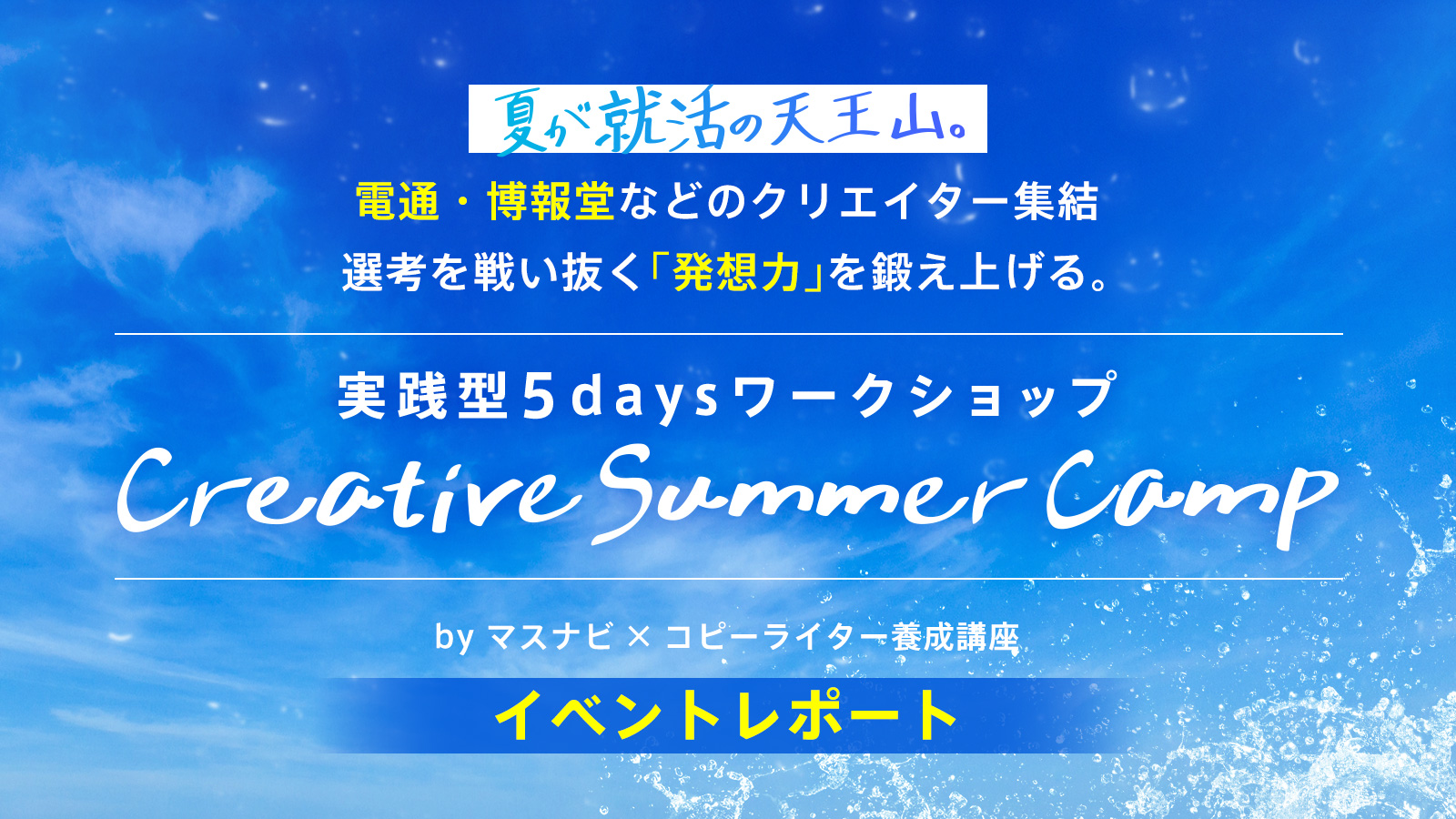
2024年9月9日から13日までの5日間で、ワークショップ「Creative Summer Camp 2024」が開催されました。株式会社宣伝会議が主催する「コピーライター養成講座」とのコラボレーション企画で、コピーライター養成講座などにて講師を務めるクリエイターを招いた講義を実施しました。
初日は電通の三島邦彦さん、2日目はアクセンチュアソング Droga5の川田貴和さん、3日目は博報堂の小島翔太さん、4日目はCHOCOLATEの市川晴華さんと豪華布陣による講義。講師自身の経歴から手掛けた案件、企画の考え方など、広告業界を目指す学生にとって今後の礎となる話が盛りだくさん。参加学生は5日間を通してチームで一つの企画を考え、最終的にプレゼンテーションを行いました。
本レポートでは、4人の講師による講義の内容を一部抜粋。参加学生のみなさんが取り組んだプレゼンテーションの様子も含めてお届けします。
Day1 電通 コピーライター 三島邦彦さん
Day2 アクセンチュアソング Droga5 ストラテジーディレクター 川田貴和さん

2日目は川田貴和さん。まずはパーパスの重要性から教えていただきました。パーパスとは、存在意義。ブランドの揺るがない価値を端的に表してアクションに転換できるように言語化したものです。つまりいつでも立ち戻れるブランドの原点であり、世の中の印象につながるものでもあり、独自のブランド価値を醸成するものです。モノや情報で溢れる時代だからこそ、ブランド独自の価値を明確にし、人々に共感してもらうことが重要。パーパスを軸に顧客との新たな関係性を築く体験やコミュニケーションが求められているとお話しをされていました。
混同しがちなパーパス・ミッション・ビジョンの違いにも触れました。「パーパスはなぜ存在しているのか。ミッションはどう実現するのか。ビジョンはどこに向かうのか」を表しています。必ずしもこの3点を定義する必要はないですが、ブランドの指針を理解して、事業のすべてに浸透させていくことが強いブランドづくりのポイントだそうです。
企画のコンセプトを考えるうえで川田さんが主に大切だと伝えていたのは3つです。1つ目は出発点。クライアントや顧客のどのような課題を解決するのかを見極めることが企画づくりにおいて一番重要だそうです。2つ目は、課題に対する解決策を導くうえで、一過性のトレンドではなく、中長期的な価値観変化を捉えることです。3つ目は、Whyを繰り返し、本質的な価値にたどり着くこと。自分の考えに対して「なぜ」を繰り返すことにより、そのコンセプトが本当にターゲットに共感されるものなのか、クライアントも納得できるものなのか検証できるとのことでした。
Day3 博報堂 クリエイティブディレクター 小島翔太さん

3日目は小島翔太さん。学生の皆さんが日常生活でしていることが、実は企画だという話からはじまりました。彼女や彼氏への誕生日サプライズも、サークルの合宿も、友人との遊びの約束も、すべて企画です。これを細かく分解すると、「誰が/誰に/いつ/どこで/どうなってほしいか」を無意識に考えているとのことでした。
企画とは「ある目的を達成するための計画を立てること」であり、「誰が」と「誰に」によってその企画の良し悪しは変わるそうです。クライアントや商品の特徴を理解し、ターゲットの生活や興味関心を把握することが必要不可欠。そして、その両者の交わる点を見つけ出すことが企画の本質となるそうです。
事例として挙げていたのは、小島さんが担当した大塚食品の炭酸飲料「マッチ」。高校生の青春を支えるブランドとして支持され続けたいがマッチの目的です。そこで今回の「誰に」を考えるうえで、より強く青春を求めている存在として男子校の高校生にフォーカス。そのアイデアを起点に、寺田心さんが男子校から共学の高校に異世界転生した青春ドラマをつくりました。男子校の生徒からみた共学の日常を描くことで、どちらの青春も見せることができ、別の世界線の青春に驚いたり、楽しんだりする様子が、今回の「誰か」である高校生たちの共感につながるのではないかと考えたそうです。
企画を考えるうえで重要なのは、新しい組み合わせを見つけること、自分の好みを活かすこと、客観性を持つこと、この3点で3日目の講義は締まりました。新しい組み合わせにより耳目を集めやすくなります。そのうえで、個人の好みや興味関心が新しい組み合わせに役立ちます。一方で、独りよがりな企画にならないように客観性を持ち、世の中とのバランス感覚が必要ともアドバイスがありました。
Day4 CHOCOLATE プランナー/クリエイティブディレクター 市川晴華さん

4日目の市川さんは就活話から。市川さんは美術系の大学に通っていましたが、企画への興味から広告業界を目指すことに。就職活動では50社以上の企業を受けたものの、失敗の連続。そんな中、ある広告会社の最終選考のインターンシップで落選濃厚な状況で、自主的に置き土産として企画書を提出したそうです。それが社長の目に止まって再選考となり、なんとか内定を掴み取ることができました。その後も企画力を武器にステップアップしてきた市川さん。その経験から、「広告業界はアイデア勝負の世界。企業規模は関係ないからこそ、小さな会社でも大手に逆転できるロマンのある仕事」と語ります。「広告クリエイターに興味があるなら、まずはなんとか広告業界に入ること。その先に続く道は無限にあるから頑張ってほしい」とエールを送りました。
広告の仕事をしている市川さんも、実は皆さんと同様に「広告はなるべく避けたいもの」だと感じているそう。スキップしたいし、見たくない。関心がない広告を、どうすれば興味を持ってもらえるのか。シンプルな問いを繰り返す仕事だと捉えているそうです。
「興味をもってもらえる」企画をつくるポイントの一つが、意外性のある組み合わせを見つけること。つまり「○○なのに✕✕」とギャップをつくることです。例として挙がったのは、「ハット会談」。イエローハット、ピザハット、リンガーハットの3社が協力して、8月10日のハットの日を話題化することで来店促進を行うキャンペーンです。3社の共通点は社名に「ハット」があるのみ。そこで、「社名に共通点があるという小粒なネタなのに、各社の代表取締役が厳かに集結して、壮大に社名の意味を確認し合う」というギャップがあるCMが生まれました。一番ありえないことを考えてみると意外と企画になることも多いと教えていただきました。
Day5 プレゼンテーション
4日間の講義・プレゼンテーション準備期間を経て、最終日は参加学生全10チームによるプレゼンテーションと講評を行いました。3人の講師からの個人賞、そして優勝チームが発表されました。
【三島邦彦賞】はGチームの便利だから何でも効率化したくなるという当たり前を捉えた「効率化された生活」という企画でした。企画内のイベントタイトルである「2045年の高校生」やキャッチコピーの「今までありがとう、無駄な時間」などを含め、随所の言葉選びが魅力的で、課題設定も面白いと高評価。ただ、企画の入口として「面白そう!」という思わせる力はあるが、コンテンツの中身が詰めきれていない部分もあり、もっとブラッシュアップできる余地があると講師陣からアドバイスがありました。
【小島翔太賞】はEチームの社内交流は居酒屋であるという当たり前を捉えて、社会人カフェを新たに提案する「脱・呑みニケーション 新・飲みニケーション」という企画でした。既存のファミレスなどとは異なり、時間制限などを含めた細かなルールを設けるなど今までにないワクワク感が評価のポイントでした。「ルールの強制力があるほど面白くなりそう」「ルールをもっと詰めてほしい」「チョコザップみたいに魅力的なネーミングがほしい」といった助言も。
【市川晴華賞】はDチームのエスカレーターの片側空けという当たり前を捉えて、両側2列乗りを促す「隣に並ぶから、立ち止まれる」という企画でした。「エスカレーターで隣通しに並んで、QRコードを同時に読み取ることでしか見ることのできない動画」という限定された視聴方法が、面白さの一部になっていて良いと講評がありました。また、日常の中に潜む暗黙の了解を変えようという着眼点も高評価につながりました。
【最優秀賞】を獲得したのは浅田玲子さん(早稲田大学)、川口ショウタさん(青山学院大学)、鈴村昇洋さん(近畿大学)、高橋響さん(デジタルハリウッド大学)、樋口菜生さん(横浜国立大学)のBチーム。

誰もが持っている「なんとなく」という気持ちは、何も考えてないとネガティブに捉えられている点から発想。そのイメージを「言語化していないからこそ、無数の可能性がある」とポジティブに捉えなおし、「あなたの人生観の象徴」として「なんとなく=あなたらしさ」と肯定していけるようにできないかと考えたそうです。そのうえで、「なんとなく就活を進めている就活生」をターゲットに、社名を匿名にして、採用キャッチコピーや事例、社員の一言などを元に自分が「いいな」と思えるものを選ぶことで、自分にマッチする企業がわかるサービスを提案しました。
審査員からは、「なんとなく」という気持ちをうまく捉えており、今回の発表チームの中で一番記憶に残ったアイデアだったと高評価。学生が企業名に左右されずに企業を選ぶことができるため、リクルーティングに悩んでいる中小企業のニーズにもマッチしそうだとの意見もありました。総合的に、アイデアの新規性と、企業・サービス側双方にとってのメリットがある点が評価され、最優秀賞となりました。
賞に選ばれたチーム以外も、自分たちなりの「当たり前」を考え抜き、5日間という短い時間の中で、メンバーと協力して一つの企画を完成することができました。
参加学生の感想
全体を通して、参加者からは下記のような感想が寄せられました。一部抜粋してご紹介します。
「『こんなにも心が動いた日を無駄にしたくない』これは、講演を聞いて勢いのままに残していた言葉です。最前線で人の心を打つ広告をつくられている講演者の皆様の言葉や人・社会・広告に向き合う姿勢に心を揺さぶられ、自分もすべての経験を元に、人の幸せを考える仕事がしたい、夢中になれる仕事をしたいと感じました」
「企画をつくる際の視点やポイント、発想の鍵をたくさん入手できました」
「広告業界を志すかけがえのない友人ができました」
「豪華な講師陣ののめり込むほどのお話や同じ方向を向く多様性のある仲間がいて、とても良い場所でした」
「広告に対して全く興味がなかったが、ワークショップを通じて広告会社のマイページ登録をするほど広告を面白いと感じました」
マスナビでは、今後も広告・クリエイティブ業界を目指す皆さまに向けてさまざまなイベントやコンテンツをお届けしていきます。
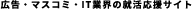

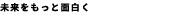


三島邦彦さんの講義から始まりました。三島さんが広告業界に興味を持ったのは、大学の講義がきっかけ。メディアパーソンによる授業で、新聞や雑誌と比べたときに広告の幅広さに惹かれたそうです。ダジャレを考えてもいい。4コママンガのようにCMコンテを考えてもいい。スーツを着なくてもいい。早起きをしなくてもいい。面白いことを考えるのが仕事で、それなら面白そうだと思って、電通に入ったそうです。
Creative Summer Campの1日目は、「コピーとは何か」から始まりました。コピーとは、クライアントを持つ言葉で、クライアントの目的を達成するための言葉。だからこそ、単なる言葉遊びや文芸にとどまらずに、クライアントの存在を意識することが必要不可欠。クライアントがいま発する価値がある言葉だと思えるかどうかが重要だと三島さんは考えているそうです。
さらに、価値を見極める洞察力や見つけた価値を共感できる形にする表現力、「これは世の中に出せる」という説得力が求められます。「相手が価値を感じることを言う」のがコピーライターの最も基本的なスタンスです。あらゆるプロジェクトに言葉は必要で、そこに必要な言葉をつくるという点で、コピーライターの役割や可能性はむしろ広がっていると考えているそうです。
「誰にでもできる発想方法はなく、頭を鍛えるしかない」と三島さんは語ります。人は一度考えたことがあることを言葉にしているゆえに、「考えたことがないことについて考えてみる」経験を多くしておくことで鍛えられるようです。本屋で自分の興味のない分野や触れたことがない分野について考えてみる。そういったアドバイスが授業ではありました。
最後に、「面白いことを考えるのは面白い」という、昔も今も変わらない仕事への思いで締めくくっていただきました。
講義後には、5日間を通して取り組む課題の発表がありました。今回の課題は「変化する時代やZ世代の価値観を捉えて、世の中の『当たり前』を変える体験」を考えること。業界・業種を規定せず難しい課題となりましたが、参加者自身の中にある「当たり前」を出し合って意見交換をする様子が見られました。